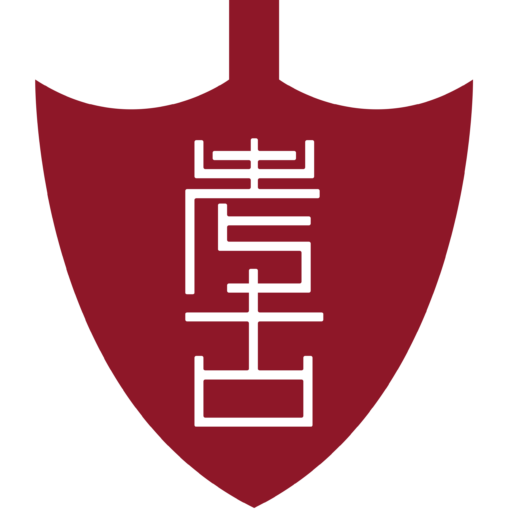『古代』バックナンバー
151・152合併号(2024年11月)
・白石浩之 有舌尖頭器の属性からみた狩猟具の様相・御堂島 正・吉川耕太郎 円筒下層式期の土坑墓に副葬された石鏃と異形石槍 石器の加熱処理と被葬者をめぐって
・小玉秀成 所謂天ヶの土器の再評価と周辺地域との関連性について
・榊田朋広 石狩低地帯南部における擦文文化初頭の集落と居住単位
・浅川滋男・武内あや莱・岡垣頼和 菅原遺跡円形建物SB140の復元に係る再検討 発掘調査報告書の刊行をうけて
・柳澤清一 渤海滅亡前後における刻符記号の拡散・紋様化と広域交差編年の検
・関口広次 日本煉瓦製造株式会社潮止工場跡とその縁辺
・瀧音 大 日本列島における琥珀製勾玉の基礎的研究
・安斎正人 私の考古学論 (4)理論考古学
・加藤一郎 三次元計測と鏡研究
150号(2023年3月)
・御堂島正「加熱処理を伴う石器製作とその前後の進行過程 ―東北地方における縄文時代遺跡の発掘調査事例を基に―」pp.1-26・青木 弘「三次元記録に基づく横穴式石室の定量的分析 ―群馬県伊勢塚古墳を対象に―」pp.27-53
・柳澤清一「アムール川中流域と北海道島・サハリン島の広域編年 ―類『 』・『簾』状紋・菱形連続紋の広域拡散から」pp.55-89
・糸川道行「平将門の乱と交通・物流」pp.91-114
148号(2021年3月)
・糸川道行「奈良・平安時代における東総の交通」pp.1-27
・西村広経「北海道島における縄文時代後期中葉の土器編年」pp.29-59
・御堂島正「風化による石器使用痕跡の表面変化 ―黒溶岩製模擬石器を用いた5年間の屋外曝露実験―」pp.61-73
147号『特集:動物・植物考古学』(2021年1月)
・樋泉岳二・佐々木由香「特集『動物・植物考古学』刊行にあたって」pp.1-6
・植月 学「縄文時代の湾奥貝塚より出土するフグ科魚類の研究」pp.7-32
・小島秀彰「縄文時代のタイムカプセル考―鳥浜貝塚が遺した課題と近年の低湿地遺跡がもたらした解―」pp.33-56
・山本 華・佐々木由香「土器圧痕からみた縄文時代のシソ属果実 」pp.57-89
・鈴木伸哉「中央区日本橋一丁目遺跡出土木製品の樹種からみた17世紀の江戸の町家における木材利用 」pp.91-114
・菅原広史「沖縄諸島貝塚時代の『特異的』なイノシシ出土傾向にみる生業様相の考察―嘉門貝塚の動物遺体の再分析を中心とした考察―」
pp.115-144
146号(2020年3月)
・板垣優河「打製石斧の使用状況に関する事例検討―長野県北村遺跡と富山県桜町遺跡―」pp.1-26
・鈴木宏和「縄紋回転技法から見た上川名式土器」pp.27-63
・佐藤亮太「資料紹介:静岡県下開土遺跡出土の縄文時代前期の土器」pp.65-78
145号『特集:土器の使用をめぐる考古学と民族学』(2019年9月)
・坪田弘子「 縄文時代中期前半における土器副葬―五領ヶ台・勝坂式土器分布圏での様相―」pp.1-36・久保田慎二・宮田佳樹・小林 正史・孫 国平・王 永磊・中村慎一「河姆渡文化の副食調理土器―学際的手法によるアプローチ―」pp.37-54
・矢澤 健「古代エジプトの供献土器に見られる精製と粗製-アブ・シール南丘陵遺跡の事例-」pp.55-77
・高橋寿光「古代エジプト,新王国時代の青色彩文土器の再利用について」pp.79-93
・中川 渚・フアン=パブロ=ビジャヌエバ・関 雄二・ダニエル=モラーレス「ペルー北部山地パコパンパ遺跡における饗宴
―出土土器の分析から―」pp.95-115
・小林正史「弥生時代から古墳前期への湯取り法炊飯の変化」pp.117-185
・徳澤啓一「タイ東北部における水利環境の変化と水甕とその用途の変遷」pp.187-204
・斎藤正憲「浅見五郎助になるということ」pp.205-217
144号(2019年5月)
・御堂島正「黒曜岩製石器の着柄・保持痕跡―各種使用法による実験痕跡研究―」pp.1-26
・板垣優河「打製石斧の機能分析―石器の装着法と掘削対象土を中心に―」pp.27-58
・佐久間正明「5世紀における土師器の並行関係について―東西における機種組成の共通性を中心に―」pp.59-80
・小畑弘己・佐々木由香・櫛原功一・ 真邉 彩・新田栄治・川島秀義・中村直子「種実・昆虫圧痕はなぜできるのか(その一)
―タイ・ラオスの土器作り村における土器作り環境調査報告―」p.81-102
・柳澤清一「『トビニダイ土器群』編年の諸問題その(3)―『忘失』されたモヨロ貝塚編年と『貝塚トレンチ』未発表資料の検討―」pp.103-155
142号(2018年7月)
・山本 華・佐藤 亮太・岩浪 陸・佐々木由香・森山 高・中野達也「埼玉県犬塚遺跡の種実圧痕から見た縄文時代前期の利用植物」pp.1-22・鈴木正博「縄紋式晩期の再葬墓(前篇)再葬の発達と『髑髏信仰』」pp.23-95
・河野摩耶・高橋和也・今津節生・南 武志「福岡県安徳台遺跡群における朱の使い分けについて」pp.97-103
・小林 嵩「下総における弥生後期集落の特質」pp.105-131
・五十嵐聡江「陸中・房の沢古墳群と山田湾の古代社会」pp.133-164
・柳澤清一「『トビニタイ土器群』編年の諸問題その(2)松法川北岸遺跡の未発表資料を中心として」pp.165-217
・竹野内恵太「初期国家社会の地域間関係と領域形成:エジプト原・初期王朝時代の副葬土器組成の分布様態から 」pp.219-253
141号『特集:古代都城造営と瓦生産』(2018年3月)
・網 伸也「特集にあたって」p.1
・清水昭博「百済の王宮と瓦生産」pp.3-28
・花谷 浩「瓦からみた飛鳥寺造営、そして飛鳥池遺跡」pp.29-49
・大脇 潔「7世紀の瓦生産:花組・星組から荒坂組まで」pp.51-88
・石田由紀子「藤原宮の造瓦体制 」pp.89-116
・今井晃樹「軒瓦からみた平城宮の造営過程」pp.117-150
・原田憲二郎「大安寺造営と瓦生産」pp.151-171
・奥村茂輝「東大寺・法華寺造営と瓦生産」pp.173-199
・上村和直「西寺・東寺の造営と瓦生産 」pp.201-220
・古閑正浩「弘仁期における平安京の瓦生産」pp.221-238
140号(2017年7月)
・御堂島正「黒曜岩製石器の耕作痕跡と発掘痕跡:農作業と発掘調査に関する実験痕跡研究」pp.1-26
・鈴木俊夫・沼澤 豊「レーザ測量図を用いた古墳当初設計の復元及び墳丘体積の計算:仲津山古墳を例として」pp.27-42
・加藤一郎「乳脚紋鏡の研究」pp.43-79
・賀来孝代「古墳時代の鵜と鵜飼の造形」pp.81-104
・柳澤清一「『トビニタイ土器群』編年の諸問題その(1)末期の段階について」pp.105-135
・今城未知「千葉県山武市旭ノ岡古墳のデジタル三次元測量」pp.137-154
139号『特集:弥生時代』(2016年5月)
・比田井克仁「特集にあたって」p.1
・杉山祐一「再葬墓出土土器の複雑性と地域間関係:千葉県塙台遺跡と周辺地域の検討から」pp.3-40
・萩野谷正宏「紀伊半島南部沿岸出土の弥生中期東海系土器の系譜」pp.41-63
・轟 直行「角江式土器の変遷と各地の併行関係」pp.65-87
・小林 嵩「下総における弥生時代中期後葉集落の特質 」pp.89-111
・白石哲也「弥生時代における鳥形土製品の役割」pp.113-136
・福田 聖「周溝内埋葬の再検討」pp.137-156
・井上慎也「群馬の大陸系磨製石器」pp.157-180
・杉山和德「東日本における鉄器研究の現状と課題」pp.181-189
・平田 健「登呂遺跡絵葉書に関する一考察:戦後日本考古学史研究序説」pp.191-213
138号『特集:民族考古学』(2016年1月)
・細谷 葵「先史時代の堅果類加工再考:世界的な比較研究をともなう民族考古学をめざして」pp.1-38
・小林 克「本州日本海沿岸北部における縄紋時代後半期の宗教儀礼:サケをめぐる考古学的事象と民俗(族)誌」pp.39-74
・高橋龍三郎「縄文後・晩期社会におけるトーテミズムの可能性について」pp.75-141
・中門亮太「土器づくり民族誌から見た土器型式の社会的背景」pp.143-176
・平原信崇「ギルマの類型化に関する一考察」pp.177-205
・山本典幸「縄文時代中期終末から後期初頭の柄鏡形敷石住居址のライフサイクル」pp.207-228
137号(2015年4月)
・金子昭彦「大洞C2式期・大型遮光器系列土偶の編年」pp.1-34・ナワビアハマッド矢麻・今城 未知「千葉県芝山町山田・宝馬3号墳の測量・GPR調査」pp.35-51
・林 正之「東北北部『末期古墳』の再検討」pp.53-87
・柳澤清一「灰白色火山灰と道東『貼付紋系土器』編年の見直し」 pp.89-104
・柳澤清一「水禽・『鰭』状モチーフから見た『貼付紋系土器』の広域編年」pp.105-139
・岩城克洋「ローマ期CCFにおける”tegame”と”teglia””testo”の関係性」pp.141-161
136号『特集:中世・近世の考古学』(2014年9月)
・平野吾郎「 中世前期における武士屋敷の一類型:寺家前遺跡の性格をめぐって」pp.1-34・相場 峻「出土板碑にみられる造立の様相:八王子市大和田山根遺跡の事例から」pp.35-64
・鈴木伸哉「台東区下谷同朋町遺跡から出土した数珠の材質と構成からみた17世紀の江戸における副葬品の様相」pp.65-86
・田口哲也 「近世火葬墓の様相」pp.87-124
・中山なな「近世江戸における子どもの墓制 」pp.125-155
・鳥越多工摩「江戸遺跡出土下駄の法量分析」pp.157-181
・中村有希「埼玉県における馬頭観世音の変遷と地域性」pp.183-214
135号『特集:世界考古学 東アジア・東南アジア』(2014年7月)
・夏木大吾「中部・関東の稜柱系細石刃石器群をめぐる地域集団の移動領域と石材ネットワーク」pp.1-18
・鈴木朋美「ベトナム中部トゥーボン川流域におけるサーフィン文化の土器編年試案:ゴーマーヴォイ遺跡
出土土器の型式分」pp.19-41
・深山絵実梨「先史時代東南アジアにおける耳飾と地域社会:3つの突起を持つ石製玦状耳飾の製作体系復
元」pp.43-65
・久保田慎二「中国新石器時代の太行山脈東側地区における土器編年と地域間関係」pp.67-102
・齋藤瑞穂「勒島式細別編年試案」pp.103-139
・韓佺・藤井康隆「清代后妃墓葬の地宮制度の特徴に関する基礎的研究 」pp.141-161
134号『特集:世界考古学 西アジア・エジプト』(2014年7月)
・赤司千恵「植物遺存体資料からみた,西アジアとその周辺の新石器時代における穀類(皮性/裸性)の選択」 pp.1-20
・熊崎真司「古代エジプトにおけるシャブティ所有点数の変化と質的変化―テーベ第1号墓の事例から―」 pp.21-43
・長屋憲慶「エジプト先・初期王朝時代の石刃剝離技術の発達と展開」pp.45-63
・山田綾乃「書体分析と分布分析によるペピ2世葬祭殿出土グラフィティの機能同定」pp.65-86
・渥美賢吾「東国における七世紀の土器から三つの断章」pp.87-115
・長山明弘「『カリカリウス土器群』の編年と当幌川遺跡出土土器の再検討」pp.117-166
133号(2014年7月)
・小林 克「東北北部縄紋時代祭祀・儀礼遺構のシンボリズムとその変遷―『性的原理』と『擬似的住居』 ―」 pp.1-38
・鈴木正博「奥東京湾方面の『栗林式縁辺文化』に学ぶ―考古年代を求め、先史集落を探り、古地域の文化動態に迫る先史考古学の回廊―」pp.39-122
・小林 嵩「下総における弥生時代中期後半~後期初頭土器編年の再検討」pp.123-141
・西野吉論「相模湾沿岸地域における弥生時代後期の集落移動に関する考察」pp.143-158
・山田俊輔「須恵器を中心とする土器祭式の系譜」pp.159-172
132号(2014年2月)
・安達香織「文様の構造と系統からみた東北地方北部縄紋時代中期後半の土器型式編年」pp.1-25・河野摩耶・南 武志・今津節生「九州北部地方における朱の獲得とその利用―硫黄同位体比分析による朱の産地推定―」pp.27-38
・加藤一郎「誉田御廟山古墳併行期の埴輪」pp.39-61
・城倉正祥・ナワビ矢麻・今城未知「千葉県横芝光町殿塚・姫塚古墳の測量・GPR調査」pp.63-98
・柳澤清一「道北編年再考その(5)紋別・枝幸・稚内における「オホーツク式土器」と擦紋土器の編年―道北・道東『地域差』編年説の見直し―」pp.99-147
・岩城克洋「イタリア半島中部におけるローマ期CCF-壺系ollaの研究」pp.149-175
131号(2013年4月)
・長山明弘「茨城県における繩紋式中期末葉・後期初頭の動物形象突起」pp.1-48
・中門亮太「東北地方北部における瘤付土器の基礎的研究」pp.49-83
・瀧音 大「背合わせ勾玉についての一考察」pp.85-108
・青木 弘「横穴式石室の基礎構造と裏込にみる古墳築造―埼玉県の事例を対象として」pp.109-141
・柳澤清一「道北編年再考その(4)礼文島浜中2遺跡(1990年度)調査資料の編年」pp.143-184
・岩城克洋「イタリア半島中部におけるローマ期CCF-浅鉢系ollaの研究」pp.185-209
129・130合併号(2012年9月)
・大脇 潔「世界の瓦―研究の一里塚(マイルストーン)―」pp.1-24
・Edward=S.=Morse(著)・大脇 潔・佐々木憲一・山本ジェームズ(訳) 「古式の焼物製屋根瓦につい
て」pp.25-76
・周藤芳幸「初期青銅器時代エーゲ海の瓦と社会―レルナの『瓦屋根の館』を中心として―」pp.77-99
・藤沢桜子「古代ローマの瓦と煉瓦」pp.101-130
・戸田有二・松本 健 ・江添 誠「西アジアの瓦塼―ヨルダン・ハシミテ王国ウムカイス遺跡出土瓦塼を
事例として―」pp.131-149
・大谷宏治「南アジアにおける瓦文化の特質 」pp.151-175
・向井佑介「中国における瓦の出現と伝播」pp.177-214
・佐川正敏「南北朝時代から明時代までの造瓦技術の変遷と変革」pp.215-239
・山形眞理子「南境の漢・六朝系瓦―ベトナム北部・中部における瓦の出現と展開―」pp.241-270
・清水昭博「韓半島三国時代における造瓦技術とその系譜」pp.271-317
・中村亜希子「渤海の瓦」pp.319-346
128号(2012年2月)
・中村信博「出流原式土器論―栃木県内遺跡の様相から見た出流原a・b式の内容・変遷と併行型式の検討」pp.1-26
・鈴木加津子「大宮台地鳩ヶ谷支台の晩期初頭の土器―土坑出土土器から見る縄紋時代後期/晩期の界線―」pp.27-47
・松丸信治「前浦式土器の再検討―千葉県における縄文時代晩期中葉の土器編年の構築―」pp.49-69
・中沢道彦「氷Ⅰ式期におけるアワ・キビ栽培に関する試論―中部高地における縄文時代晩期後葉のアワ・キビ栽培の選択的受容と変化―」pp.71-94
・齋藤瑞穂「新潟市法花鳥屋B遺跡『重弧縄線文土器』小考」pp.95-111
・柳澤清一「いわゆる『元地式』(『接触様式』)編年の再検討」pp.113-160
・田口哲也「都市と村落の近世墓―甕棺の環境的・地域的視点からの比較研究―」pp.161-200
・宮里 修「コマ形土器から花盆形土器へ」pp.201-221
127号(2012年1月)
・鈴木正博「貝塚遺蹟に学ぶ(序説)―『巨大斜面貝塚』出現以前の古鬼怒湾『貝塚文化』―」pp.1-85・渡辺 明・上野修一「茨城県東浦遺跡の土版と土偶」pp.87-102
・比田井克仁「土器移動と伝統性継承の背景」pp.103-127
・佐久間正明「東国における古墳出土袋斧形石製模造品の製作方法と展開」pp.129-162
・柳澤清一「ウサクマイN遺跡出土のソーメン紋土器の年代―土器から見た『B-Tm』火山灰の疑問点―」pp.163-194
・小野本敦「『瓦生』と記された文字瓦」pp.195-203
126号(2011年11月)
・鈴木正博「土偶に学ぶ―関東北晩期土偶の再編と『土偶インダストリ論』の現在―」pp.1-62・小出輝雄「続・環濠は戦争用遺構か―戦争(戦い・いくさ)への有効性・土塁の性格を中心として―」pp.63-79
・小西正彦「古墳時代前期における仿製鏡製作技術の一側面―同工鏡群での面径と重さの関係より―」pp.81-99
・柳澤清一「旧常呂町・斜里町における新北方編年案の検―『Ma-b』・『Km-5a』火山灰を 『鍵』層として―」pp.101-150
・柳澤清一「新北方編年案とB-Tm火山灰から見た蕨手刀の副葬年代―青苗砂丘遺跡から目梨泊遺跡・モヨロ貝塚へ―」pp.151-189
125号『特集:世界の考古学 ものから読む社会』(2011年8月)
・久保田慎二「墓からみた馬家浜文化の地域性」pp.1-23
・小澤正人「河南省淅川県李官橋盆地における春秋戦国時代墓葬についての一考察」pp.25-46
・和田久彦「北西シリアの鉄器時代の住居と集落に関する一考察―テル・マストゥーマの遺構をもとにして―」pp.47-68
・河合 望「葬制から探る古代エジプト第2中間期末から新王国時代初期の社会様相の一側面―アブ・シール南丘陵遺跡出土の集団埋葬を中心として―」pp.69-96
・真道洋子「イスラーム・ガラスにみる8世紀における社会の変容と展開―フスタート遺跡とラーヤ遺跡を中心に―」pp.97-118
・森下壽典「南米インカ国家における土器生産と工人集団についての基礎的検討」pp.119-154
124号(2010年9月)
・鈴木正博「『生態型式学』の構えと実践―縄紋式前期の『彩色文様帯』と漆―」pp.1-40・長山明弘「加曾利E(新)式における土器系列の研究(1)『連弧文土器』から『Y字状文土器』へ」pp.41-95
・柳澤清一「道北編年の再検討その(3)『南貝塚式』から見た環宗谷海峡編年案の検討―道央から礼文島・モネロン・サハリン島へ―」pp.97-132
・齋藤瑞穂「北部九州における前期弥生壺の文様帯・雑考」pp.133-148
123号(2010年3月)
・鈴木素行「続・部田野のオオツタノハ―茨城県域における弥生時代『再葬墓後』の墓制について―」pp.1-51・齋藤瑞穂「下戸塚式という視点」pp.53-71
・比田井克仁「弥生後期社会の系譜類型と古墳時代への移行」pp.73-109
・太田博之「朝鮮半島起源の服飾・器物を表現する埴輪について」pp.111-127
・中澤寛将「渤海の食器様式と土器生産」pp.129-154
122号(2009年3月)
・石井智大「弥生時代L字状石杵の歴史的意義―辰砂・水銀朱の流通をめぐって」pp.1-24
・福田 聖「関東地方における『周溝』の研究をめぐって」pp.25-51
・柏木善治「葬送に見る横穴墓の機能と構造変化―神奈川県における改葬の事例を中心として―」pp.53-78
・柳澤清一「道北における北方編年の再検討その(2)新しい青苗砂丘遺跡編年と北方古代史研究」pp.79-121
・榊田朋広「土器容量組成からみたトビニタイ文化と擦文文化の関係」pp.123-153
・宮里 修「朝鮮半島の銅矛について」pp.155-179
・遠部 慎・宮田佳樹・小林謙一「竪穴住居覆土内における混入の検討」pp.181-192
121号(2008年3月)
・村越純子「剥片尖頭器の形態と分類」pp.1-22・小西正彦「同笵・同型鏡における重さの差異について― 三角縁神獣鏡の場合―」pp.23-59
・加藤一郎「銅鏃の製作方法に関する覚書―衛門戸丸塚古墳出土品について―」pp.61-74
・宮下孝優「古代・武蔵国府関連遺跡の竪穴建物跡―地域別にみた規格性―」pp.75-110
・江崎 武「下古館遺跡の再検討―東国における中世墓の実相―」pp.111-124
・鈴木建治「炉周辺の人間活動―シベリア・エニセイ川上流域・ウイ2遺跡・発掘区3・第2文化層出土の遺物集中部を対象として―」pp.125-145
120号(2007年3月)
・村上 昇「日本列島東部における縄文時代草創期隆起線文土器の編年―関東地域を中心に―」pp.1-28・金子昭彦「渡辺仁『縄文土偶すなわち家の神』説の検証―仮説検証法による解釈検証試論―」pp.29-62
・山崎 健・織田銑一「 縄文時代後晩期における貝輪素材の獲得と搬入に関する研究―愛知県伊川津貝塚出土のタマキガイ科製貝輪の分析から―」pp.63-86
・菊池有希子・三好伸明「弥生時代の米収穫量について―元水田における実験考古学的研究―」pp.87-107
・小野本敦「古墳時代中期における埴輪生産組織の一様相―狛江市土屋塚古墳の同工品分析から―」pp.109-122
・市毛 勲「豊後丹生の岩石層中の横穴群―日本古代・中世の水銀鉱業の研究―」pp.123-130
119号(2006年3月)
・加藤 学「妙高山麓における縄文時代中期前葉の玉髄製小形石錐―和泉A遺跡下層・大久保遺跡出土資料の使用痕観察を中心に―」pp.1-23・岡本孝之「青森県の白川型石斧」pp.25-55
・小出輝雄「環濠は戦争用遺構か―南関東弥生時代中期後半期の検討から―」pp.57-77
・柳澤清一「道北における北方編年の再検討その(1)モヨロ貝塚から内路・上泊遺跡へ」pp.79-122
・庄田慎矢「比來洞銅剣の位置と弥生歴年代論(下)」pp.123-158
・藤井康隆「晋式帯金具補考」pp.159-172
118号(2005年3月)
・吉田政行「相模野台地を中心とする後期旧石器時代開始期前後の石材獲得・消費行動」pp.1-30・忍澤成視「いわゆる『舌状貝器』について―果たして意図して作られた利器か、その存在理由をさぐる―」pp.31-43
・比田井克仁「東日本における磐座祭祀の淵源」pp.45-77
・魚津知克「鉄製農工具の副葬と農工具形石製祭器の副葬」pp.79-103
・井上裕一「人物埴輪の構造と主題(2)表象による序列の表現」pp.105-140
・志賀 崇「尾張の簾状重弧紋軒平瓦」pp.141-160
117号(2004年12月)
・庄田慎矢「比來洞銅剣の位置と弥生暦年代論(上)」pp.1-29
・比田井民子「東日本を中心とする後期旧石器時代初頭の小形剥片石器群」pp.31-51
・佐久間正明「福島県における五世紀代古墳群の研究―石製模造品を通した正直古墳群の分析を中心に―」pp.53-81
・賀来孝代「鵜飼・鷹狩を表す埴輪」pp.83-105
・大西雅也「羨門部に切石組構造をもつ横穴墓について―多摩川下流域左岸の事例から―」pp.107-120
・鶴間正昭「関東からみた東海の諸窯」pp.121-151
116号(2004年11月)
・松田光太郎「縄文時代前期の小形石棒に関する一考察」pp.1-17
・阿部友寿「遺構更新における骨類の出土例―縄文時代後晩期における配石遺構・墓坑・焼人骨―」pp.19-42
・谷口 肇「『細密条痕』の復元」pp.43-85
・岩本 崇「副葬配置からみた三角縁神獣鏡と前期古墳」pp.87-112
・比田井克仁「地域政権と土器移動―古墳時代前期の南関東土器圏の北上に関連して―」pp.113-130
・井上裕一「人物埴輪の構造と主題(1)表象の分類と構成」pp.131-163
115号(2004年5月)
・松田光太郎「縄文時代前期の小形石棒に関する一考察」pp.1-17・阿部友寿「遺構更新における骨類の出土例―縄文時代後晩期における配石遺構・墓坑・焼人骨―」pp.19-42
・谷口 肇「『細密条痕』の復元」pp.43-85
・岩本 崇「副葬配置からみた三角縁神獣鏡と前期古墳」pp.87-112
・比田井克仁「地域政権と土器移動―古墳時代前期の南関東土器圏の北上に関連して―」pp.113-130
・井上裕一「人物埴輪の構造と主題(1)表象の分類と構成」pp.131-163
114号(2004年1月)
・遠部 慎「九州における押型文土器出現期(予察)」pp.1-20・金子昭彦「結髪土偶と刺突文土偶の編年―東北地方北部における縄文時代晩期後葉の大形土偶―」pp.21-50
・坂口 隆「砂丘遺跡における廃棄パターンと行動分析―北海道礼文町浜中2遺跡R地点の事例研究から―」pp.51-70
・鈴木正博「『橿原式』から『唐古式』へ―『木葉文』生成への型式構えは如何にして形成されたか―」pp.71-96
・藤田 尚「沖縄県木綿原人骨の歯科古病理学的検討」pp.97-104
・沼澤 豊「古墳築造企画の普遍性と地域色栃木県における基壇を有するとされる古墳をめぐって」pp.105-162
113号『特集:石器使用痕研究の現在』(2003年5月)
・御堂島正「特集にあたって」pp.1・五十嵐彰「『使用』の位相―使用痕跡研究の前提的諸問題―」pp.3-18
・御堂島正「使用痕光沢面論争叢の行方」pp.19-39
・澤田 敦「石器のライフヒストリー研究と使用痕分析」pp.41-55 ・山田しょう「テクノロジー,社会関係,社会的再生産―使用痕研究の唯物論的展開―」pp.57-74 ・伊藤典子「ナイフ形石器の機能推定―福島県塩坪遺跡出土石器を中心とした使用痕分析―」pp.75-96 ・池谷勝典「礫石器の使用痕研究―磨石類を中心として―」pp.97-114 ・原田 幹「石製農具の使用痕研究―収穫に関わる石器についての現状と課題―」pp.115-138 ・平塚幸人・斎野裕彦「片刃磨製石斧の形態と使用痕―宮城県名取市原遺跡出土資料を中心として―」pp.139-163 ・高瀬克範・丸山浩治「中半入遺跡における古墳時代の黒曜石製石器―1D区『105号住居跡』出土資料の検討―」p.165-183
112号(2004年7月)
・藤田 尚「古病理学・古疫学からみた縄文人―縄文人は豊かな狩猟採集民か? ―」pp.1-11・南 久和「安行式前半」pp.13-51
・友廣哲也「北関東古墳時代前期土師器の様相から見た古墳時代社会の成立」pp.53-85
・増田一裕「いわゆる前方後円墳規格の出現に関する諸問題」pp.87-119
・佐々木幹雄・余語琢磨 「須恵器の色―実験的技術復元と理化学的分析に関する考察―」pp.121-150
・今野春樹「遼代契丹墓出土馬具の研究」pp.151-176
111号(2002年12月)
・本橋恵美子「縄文時代における石器集中部の検討―石器製作址と立地について―」pp.1-14・阿部常樹「貝類採集活動からみた縄文時代後期大型馬蹄形貝塚成立過程について―千葉県葛南地域における例―」 pp.15~40
・渡辺清志「複式炉と柄鏡―縄文時代中期末葉~後期初頭における二者―」pp.41-62
・中沢 道彦・丑野 毅 ・松谷暁子「山梨県韮崎市中道遺跡出土の大麦圧痕土器について―レプリカ法による縄文時代晩期土器の籾状圧痕の観察(2)―」pp.63-83
・南 久和「編年表と仮設年代―放射性炭素年代測定の前に―」pp.85-93
・笹生 衛「古代仏教の民間における広がりと受容」pp.95-126
・藤井康隆「晋式帯金具の製作動向について―中国六朝期の金工品生産を考える―」pp.127-149
110号『特集:古代における寺の空間構成』(2002年12月)
・山路直充「特集にあたって」p.1
・小沢 毅「藤原京の条坊と寺院占地」pp.3-21
・網 伸也「畿内における在地寺院の様相」pp.23-44
・石毛彩子「平城京内寺院における雑舎群」pp.45-71
・木下 良「国分寺と条里」pp.73-99
・山路直充「国分寺における寺院地と伽藍地(上)」pp.101-142
・久保智康「古代山林寺院の空間構成」pp.143-167
・篠原英政・田中弘志「弥勒寺跡・弥勒寺東遺跡―美濃国武義郡衙と郡寺―」pp.169-193
・辻 史郎「下総国結城廃寺の伽藍配置と瓦について」pp.19-220
・昼間孝志「武蔵寺内廃寺の空間構成」pp.221-232
・川尻秋生「資財帳からみた伽藍と大衆院・政所」pp.233-244
・山口英男「古代荘園図に見る寺域の構成―額田寺の伽藍と寺領―」pp.245-265
・吉田一彦「『元興寺縁起』をめぐる諸問題―写本・研究史・問題点―」pp.267-288
・岡野浩二「平安時代の造寺行事所」pp.289-307
109号(2001年2月)
・忍澤成視「縄文時代におけるタカラガイ加工品の素材同定のための基礎的研究―いわゆる南海産貝類の流通経路解明にむけて―」pp.1-76・比田井克仁「関東弥生首長の相対的位置づけとその成立過程」pp.77-100
・大脇 潔「十能瓦考-瓦の伝播と自生―」pp.101-124
・宮里 修「朝鮮半島の銅剣について」pp.125-159
・鈴木正博「金子浩昌の考古学とは?―その理念と方法に接近可能な知的インデックスの完成―」pp.161-168
108号(2000年3月)
・中村五郎「平栫・塞ノ神型式群土器について」pp.1-25・植月 学・小島秀彰「縄文前期の生業と居住形態―千葉県庚塚遺跡の生業活動とその季節性―」pp.27-57
・柳澤清一「武蔵野台地周辺における縄紋後期初頭土器の成立(予察)称名寺1式と続加曽利E4式のあいだ」pp.59-92
・佐々木由香「縄文時代の『水場遺構』に関する基礎的研究」pp.93-127
・福田正宏「北部亀ヶ岡式土器としての聖山式土器」pp.129-158
・松本太郎・松田礼子「千葉県市川市木戸口遺跡の須和田期集落について」pp.159-170
107号(1999年9月)
・柳澤清一「神奈川県における縄紋中期末葉編年の検討」pp.1-42・鈴木克彦「北海道渡島・桧山地域の後期後半の編年―北海道西南部の縄文後期の編年学的研究(3)―」pp.43-63
・藤田 尚「縄文人の歯周疾患―歯の生前喪失数と齲歯数の関係の検討を中心―」pp.65-76
・太田 博之「千葉県畑沢埴輪窯出土馬形埴輪に見る面繋の構造」pp.77-89
・高井佳弘「上野国分寺跡出土の郡郷名押印文字瓦について」pp.91-118
・後藤雅彦「東南中国の片刃石斧考」pp.119-144
・余語琢磨「バリ島東部の土器生産と流通―旧4王国の支配地域にみる生業の動態―」pp.145-168
106号(1999年3月)
・柳澤清一「東京都における縄紋中期末葉編年の検討」pp.1-40・鈴木正博「本邦先史考古学における『土器型式』と縦横の『推移的閉包』―古鬼怒湾南岸における弥生式後期『下大津式』の成立と展開―」pp.41-114
・安藤広道「弥生土器の『絵画』と文様―横浜市折本西原遺跡出土『絵画』土器の紹介をかねて―」pp.115-139
・戸根貴之「古代文字資料にみる蝦夷」pp.140-163
・金子 智「江戸遺跡出土資料に見る近世海鼠瓦の諸様相」pp.164-180
105号『特集:前期古墳の諸問題』(1998年8月)
・森下章司 「古墳時代前期の年代試論」pp.1-27・一瀬和夫「古墳時代前期における円筒埴輪生産の確立」pp.29-48
・林 裕己「三角縁神獣鏡の銘文―銘文一覧と若干の考察」pp.49-74
・清喜裕二「初期農工具形石製模造品の基礎的研究―大形石製刀子を中心として―」pp.75-100
・森田克行「青龍三年鏡とその伴侶–安満宮山古墳出土鏡をめぐって」pp.101-113
・青木勘時「大和東南部の前期古墳について―天理市東殿塚古墳の調査成果を中心に―」pp.115-128
・中屋克彦「石川県鹿西町雨の宮1号墳の発掘調査」pp.129-138
・柳沼賢治「福島県郡山市大安場1号墳の発掘調査」pp.139-147
・吉田正人・高橋克壽・魚津知克 「岐阜県可児市前波長塚古墳・野中古墳の発掘調査」pp.149-164
・中井正幸「美濃昼飯大塚古墳の研究(II)墳頂面調査の一事例」pp.165-181
・荒川史・魚津知克・内田真雄「京都府宇治市庵寺山古墳の発掘調査」pp.183-197
104号(1997年12月)
・佐々木憲一「日本考古学における中位理論―弥生・古墳時代の地域間交流論を素材にして―」pp.1-18・会田容弘「東北地方縄文時代後期から晩期の土器装飾文様に見られる2種のキザミ」pp.19-41
・藤田 尚「愛知県渥美半島出土の縄文時代人骨の抜歯―抜歯の施術年齢および加齢変化の検討を中心として―」pp.42-63
・友廣哲也「石田川式土器考」pp.64-91
・糸川道行「房総の有段口縁坏・比企型坏」pp.92-115
・辻 史郎「千葉県武士遺跡出土瓦に関する一考察」pp.116-139
103号(1997年5月)
・柳澤清一「西日本における縄紋時代後期中葉編年の検討―津雲A式・彦崎K1式から小池原上層式・鐘崎式・平城式へ―」pp.1-50・南 久和「葉脈状文」pp.51-98
・比田井克仁「弥生時代後期における時間軸の検討―南武蔵地域の検討を通して―」pp.99-134
・次山 淳「初期布留式土器群の西方展開―中四国地方の事例から―」pp.135-156
・杉山晋作・井上裕一・日高 慎「古墳時代の横坐り乗馬」pp.157-186
・櫻木晋一「中世の銭貨鋳型についての一考察」pp.187-199
・菊池徹夫「書評 『画龍点睛』―山内清男先生没後25年記念論集―」pp.200-201
102号(1996年10月)
・安斎正人「考古学における構造変動論」pp.1-14・佐藤宏之「狩猟システムのエスノアーケオロジー―ロシア沿海州ウデへの民族調査から―」pp.15-35
・堤 隆「削片系細石刃石器群をめぐる技術的組織の異相―中ッ原細石刃石器群を中心として―」pp.36-61
・柳澤清一「東日本における縄紋中・後期の大別境界と広域編年軸の検討」pp.62-105
・片岡宏二「渡来人と青銅器生産―佐賀平野の渡来人集落を中心として―」pp.106-127
・友廣哲也「群馬県の北陸土器と古墳時代集落の展開」pp.128-148
・永井宏幸「古代木製鐙小考―愛知県一宮市大毛沖遺跡出土例の位置付け―」pp.149-15
101号(1996年5月)
・阿子島香「マドレーヌ文化期における適応戦略と遺跡構造分析」pp.1-29・比田井民子「石材から考える集団領域とその規模」pp.30-56
・伊藤 健「中部ナイフ形石器文化地域圏の確立」pp.57-82
・柳澤清一「縄紋後期初頭末~中葉における広域編年軸の検討―伊勢寺・芥川・鶴来が元・十合野遺跡等の新資料より―」pp.83-112
・藤岡孝司「古代東国村落の構造―中核集落と衛星集落―」pp.113-143
・金子 智「江戸遺跡出土資料に見る近世軒平瓦・軒桟瓦の地方色」pp.144-160
・小川 望「焼塩壷の“生産者”に関する一考察―『泉州磨生』の刻印をもつ焼塩壷を例として―」pp.161-186
100号(1995年9月)
・菊池徹夫「序―『古代』第100号を祝す―」pp.1-3・田中新史「使用具の古墳埋納(下)」pp.5-87
・比田井克仁「二重口縁壺の東国波及」pp.88-117
・友廣哲也「櫛描文文化圏の弥生時代終末から古墳時代初頭期の墓制」pp.118-142
・鈴木正博「茨城弥生式の終焉―『続十王台式』研究序説」pp.143-201
・杉山晋作「人物埴輪を供された被葬者層」pp.202-238
・井上裕一「形象埴輪製作者と馬形埴輪」pp.239-313
・宮崎由利江「埼玉古墳群の水鳥形埴輪の意義」pp.314-344
・太田博之「句兵を表現する埴輪」pp.345-356
・「『古代』投稿規定および執筆要項」pp.16-17
・市毛 勲「『古代』第100号の回顧」pp.14-15
・「『古代』の総目次(第51号~第100号)」pp.p1-13
99号(1995年3月)
・鈴木正博「『大平山元I式土器』への接近―たかが『無文土器』,されど『無文土器』―」pp.1-36・鈴木加津子「飛騨桜洞遺跡の大洞C₂式土器」pp.37-47
・豆谷和之「前期弥生土器出現」pp.48-73
・谷口 肇「『貝包丁』への疑義」pp.74-98
・石橋広和「弥生終末期における和泉南部地域の集落遺跡の変化―泉南市岡田東遺跡とその存在の意義について―」pp.99-113
・亀谷弘明「伊豆国の荷札木簡と(膳)大伴部」pp.114-131
・柳澤清一「『日本古代文化学会』と歴史教科書の編纂―少国民新聞編『新しい日本の歴史』第1巻とその周辺―」pp.132-164
98号(1994年9月)
・菊池徹夫「滝口先生追悼論集の発刊にあたって」pp.1-2・鈴木正博「黒潮と『加治屋園式土器』」pp.3-33
・柳澤清一「西日本縄紋後期前葉編年の再検討―近畿地方を中心として―」pp.34-109
・友廣哲也「北関東の古墳時代文化の受容」pp.110-135
・田中新史「使用具の古墳埋納(上)」pp.136-156
・佐々木幹雄「還元焰小考―発色の視点から―」pp.157-177
97号『特集:古代における同笵・同系統軒先瓦の展開』(1994年3月)
・森 郁夫「古代における同笵・同系軒瓦」pp.1-20・辻 秀人「陸奥国における雷文縁複弁四弁,単弁八弁蓮華文軒丸瓦の展開について」pp.21-41
・真保昌弘「陸奥国南部に分布する二種の複弁系鎧瓦の歴史的意義について」pp.42-56
・大橋泰夫「下野薬師寺の軒先瓦とその同系瓦」pp.57-69
・須田 勉「国分寺造営期にみる中央と在地―上総国分寺改作期の造瓦から―」pp.70-98
・平野吾郎 「遠江国分寺の造営と地方豪族の動向」pp.99-114
・梶山 勝「尾張・三河の同笵・同系軒瓦–古代寺院と瓦窯を中心として」pp.115-142
・土山公仁「美濃地方の同笵瓦と複弁蓮華文軒丸瓦」pp.143-164
・久保智康「北陸南西部における軒瓦の受容と伝播-―越前地域を中心に―」pp.165-192
・網 伸也「北白川廃寺の造営過程―北山背古代寺院の考古学的考察―」pp.193-223
・大脇 潔「飛鳥時代初期の同笵軒丸瓦―蘇我氏の寺を中心として―」pp.224-245
・藤井保夫「紀伊の白鳳寺院における川原寺式・巨勢寺式軒瓦の採用について」pp.246-269
・伊藤 晃「備中式瓦について」pp.270-279
・妹尾周三「横見廃寺式軒丸瓦の検討―いわゆる『火焰文』軒丸瓦の分布とその背景」pp.280-308
・内田律雄「西山陰の同紋様系古瓦」pp.309-318
・亀田修一「地方への瓦の伝播―伊予の場合―」pp.319-355
・高橋 章「豊前の同系瓦考」pp.356-372
96号(1993年9月)
・鈴木正博「『向ノ原B式土器』の再吟味」pp.1-26・柳澤清一「『日本先史土器図譜』以前の列島縄紋式編年の原案―陸前・関東・吉備の中期末葉から後期初頭を中心として―」pp.27-65
・大橋泰夫「古墳時代中期における大刀の系譜」pp.66-73
・水野敏典「古墳時代後期の軍事組織と武器副葬―長頸鏃の形態変遷と計量に見る武器供給から―」pp.74-104
・石坂俊郎「千葉県柏市戸張城山遺跡の評価にむけて―1986年調査の報告を中心に―」pp.105-132
・荻 悦久「千葉県多古町しゃくし塚古墳出土の有段口縁壺」pp.133-141
・平山誠一・椎名信也・車崎正彦「千葉県山武郡山武町の前期古墳―島戸境1号墳発掘調査速報―」pp.142-147
・小出紳夫・西川修一・山路直充「千葉県印西町木下別所廃寺の鎧瓦」pp.148-157
95号『特集:縄紋文化の解体―縄紋式から弥生式へ―』(1993年3月)
・『古代』第95号編集担当「『特集 縄紋文化の解体』について」pp.1-11・吉田 寛「大分市稙田市遺跡出土の縄文晩期土器―特殊な鉢形土器の紹介を中心に―」pp.12-23
・中村修身「弥生系石器の成立にみる初期稲作農耕社会」pp.24-49
・野口哲也「近畿地方縄文時代晩期終末突帯文土器の二態」pp.50-65
・小田野哲憲「東北北部縄文時代末期・弥生時代初頭の遺構と遺物」pp.66-88
・田部井功「大洞A2式に関する覚書」pp.89-113
・金子昭彦「大洞C2式の土偶―大形土偶の変化を中心として―」pp.114-165
・南 久和「工字状文」pp.166-207
・石川日出志「鳥屋2b式土器再考―六野瀬遺跡出土資料を中心に―」pp.208-225
・柴田俊彰「東北南部における縄文時代晩期後葉集落の一様相―福島県南諏訪原遺跡―」pp.226-252
・鈴木加津子「安行式文化の終焉(四・完結編)」pp.253-310
・鈴木正博「荒海貝塚文化の原風土」pp.311-376
・谷口 肇「弥生文化形成期における相模の役割」pp.377-405
・青木幸一「『縄文時代晩期終末』現状と課題―主に関東地方とその周辺―」pp.406-450
・中山清隆「朝鮮・中国東北の突帯文土器」pp.451-464
94号(1992年9月)
・鈴木正博「『武者ヶ谷式土器』の意義」pp.1-18・柳澤清一「加曾利E(新)式編年研究の現在」pp.19-58
・山本孝司「加曾利E3-4式と曾利V式について―神奈川県新戸遺跡出土資料を再検討して―」pp.59-84
・本橋恵美子「『埋甕』にみる動態について―縄文時代中期後半の遺跡の検討から―」pp.85-126
・市毛美津子「『凸多面体磨き石』について」pp.127-159
・鈴木加津子「安行式文化の終焉(3)」pp.160-181
・西川修一「特殊壺になれなかった壺」pp.182-223
・友廣哲也「群馬県の古墳文化初頭期の検討」pp.224-242
・桜岡正信・佐々木幹雄「黒色土器の吸炭処理について―その実験的考察―」pp.243-257
93号(1992年3月)
・西村正衛「滝口宏先生追悼文」pp.1-2・菊池徹夫「滝口宏先生追悼文」pp.2-4
・松田光太郎「浮島式土器の成立について―東関東における縄文時代前期後半の土器文様の伝統―」pp.5-59
・水野敏典「群集墳の一形態としての横穴墓―西嶋定生の『古墳と大和政権』にみる横穴墓解釈の検討―」pp.60-89
・小澤重雄「『貝床』を持つ古墳・横穴について」pp.90-100
・網 伸也「後期難波宮と古代寺院」pp.101-127
・澤井 玄「『トビニタイ土器群』の分布とその意義」pp.128-151
92号(1991年9月)
・日野一郎「神奈川県における考古学研究と早稲田大学 」pp.1-11・鈴木正博「『寺尾式土器』の再吟味―大塚達朗『窩紋土器研究序説(前篇)』の思惑違」pp.12-78
・御堂島正「石鏃と有舌尖頭器の衝撃剥離」pp.79-97
・山本暉久「縄文時代における異系統土器群流入の実相―神奈川における早期末葉から中期初頭期の東海系土器群の流入をめぐって―」pp.98-140
・柳澤清一「神奈川県加曾利E式後半編年の再検討―加曾利E3-4式期を中心として―」pp.141-196
・長岡史起「神奈川県の縄文時代遺跡分布とその変遷―傾向面からわかることと推定される『真の分布』―」pp.197-215
・谷口 肇「神奈川『宮ノ台』以前」pp.216-262
・西川修一「弥生の路・古墳の路―神奈川の場合―」pp.263-289
・長谷川厚「古墳時代後期土器の生産について―特に神奈川県内の古墳時代後期土師器の生産構造について―」pp.290-320
・小林公治「古代集落の食生活と生業―草山遺跡と三ッ俣遺跡の検討を通じて―」pp.321-368
・余語琢磨「『𤭖』名をもつ須恵器」pp.369-389
91号『地域特集(7)―神奈川県―』(1991年3月)
・柳澤清一「『榎林式』から『最花式』(中の平III式)ヘ―陸奥中期後半編年の再検討―」pp.1-46・鈴木加津子「安行式文化の終焉(2)」pp.47-113
・西本豊弘「縄文時代のシカ・イノシシ狩猟」pp.114-132
・鈴木正博「栃木『先史土器』研究の課題(2)」pp.133-171
・比田井克仁「古墳出現段階における伝統性の消失―伝統的文様壺から見た場合―」pp.172-207
90号(1990年10月)
・比田井民子「角錐状石器の地域的動態と編年的予察」pp.1-37・倉田恵津子「下総台地周辺における大形石棒について」pp.38-52
・浜野美代子「縄文土偶の基礎研究」pp.53-73
・鈴木加津子「安行式文化の終焉(1)」pp.74-100
・笹森紀己子「弥生壺口縁内文様帯論」pp.101-110
・本田光子「石杵考」pp.111-140
・小島敦子「墓域からみた集落論研究の基礎操作」pp.141-168
・寺沢知子「石製模造品の出現」pp.169-187
・宮崎由利江「馬形埴輪に伴出する人物埴輪について」pp.188-205
・水口由紀子「奈良・平安時代の伊豆諸島における漁撈活動の特質」pp.206-229
・岡田淳子「民族考古学の一試論」pp.231-242
・張替いづみ「エジプト・ナカダ文化期の牙形象牙製品について」pp.1-20
89号『地域特集(6)―栃木県―』(1990年3月)
・塚本師也「北関東・南東北における中期前半の土器様相」pp.1-36・上野修一・津布樂一樹「栃木県土偶出土遺跡 地名表並資料集成」pp.37-60
・藤田典夫「那珂川中流域における弥生時代初頭の土器様相」pp.61-77
・鈴木正博「栃木『先史土器』研究の課題(一)」pp.78-117
・篠原祐一「石製模造品観察の一視点」pp.118-128
・水沼良浩「塚山古墳群とその周辺」pp.129-150
・大橋泰夫「下野における古墳時代後期の動向」pp.151-186
・進藤敏雄「栃木県の群集墳の一様相」pp.187-207
・穴沢咊光・馬目順一「足利市西宮町長林寺裏古墳(機神山22号墳)出土の双龍環頭大刀」pp.208-226
・小森哲也・梁木誠「真岡市根本神宮寺塚古墳出土の『塼』をめぐって」pp.227-252
・津野 仁「地方官衙跡出土の墨書土器」pp.253-267
・山路直充「下野薬師寺跡の伽藍(試論)」pp.268-291
88号(1989年9月)
・伊藤 健「通常剥離を有する尖頭器の編年と変遷」pp.1-40・鈴木正博「縄紋草創期研究の序」pp.41-83
・柳澤清一「東北縄文中・後期編年の諸問題」pp.84-107
・前沢輝政「創出期古墳の墳形と規模の規格性について」pp.108-125
・田中新史「奈良盆地東縁の大型前方後円墳出現に関する新知見」pp.126-136
・中司照世・田中新史「岸和田市久米田貝吹山古墳最終の車輪石」pp.137-144
・市毛 勲「飛鳥酒船石『朱造石』説について」pp.145-153
・長谷川厚「歴史時代墳墓の成立と展開(三)」pp.154-176
・小沢正人「東周期副葬礼器の表すもの」pp.177-194
・工藤元男「雲夢睡虎地秦墓簡『日書』より見た秦・楚の二十八宿占い」pp.195-215
87号『地域特集(5)―埼玉県2―』(1989年3月)
・細田 勝「黒浜式土器成立の背景について―特に東北地方土器群との対比を通して―」pp.1-48・鈴木正博「安行式土偶研究の基礎」pp.49-95
・田部井功「安行式と須和田式土器の間(一)」pp.96-118
・小林茂・吉川國男「秩父市下ッ原遺跡の調査(ニ)」pp.119-152
・笹森紀己子「小型器台土器に関する覚書」pp.153-171
・斎藤国夫「埼玉県行田市酒巻十四号墳の埴輪配列について」pp.172-188
・杉崎茂樹「北武蔵の大規模群集墳の消長に関する一考察」pp.189-200
・市毛 勲「武蔵国入間郡の郡衙について」pp.201-215
・佐々木幹雄「一地方武士団とその開発 ―十二世紀、武蔵国児玉党の場合―」pp.216-253
・田中裕子「近代浅瓦の制作技法」pp.254-269
86号『地域特集(4)―東海―』(1988年9月)
・伊勢野久好「三重県の前方後円墳」pp.1-7・中井正幸「岐阜県西濃地方の前方後円墳」pp.8-15
・長瀬治義「岐阜県東濃地方の前方後円墳」pp.16-23
・服部哲也「愛知県尾張地方の前方後円墳」pp.24-36
・贄 元洋「愛知県三河地方の前方後円墳」pp.37-55
・東海古墳文化研究会「岐阜県西濃地方の前方後方(円)墳の測量調査」pp.56-83
・赤塚次郎「東海の前方後円墳」pp.84-109
・中司照世「福井県の前方後円墳」pp.110-122
・石黒立人「伊勢湾地方と琵琶湖地方、あるいは東西の結節点―弥生後期の土器様相を中心として―」pp.123-150
・宮腰健司「宮之脇遺跡第2号住居跡出土土器について」pp.151-158
・加納俊介・浅野清春・北村和宏「愛知県岩倉市小森遺跡出土の土器」pp.159-186
・鈴木正博「コメント① 十王台式土器について」pp.187
・笹澤 浩「コメント② 箱清水式土器について」pp.188
・北村和宏「付論 柳ヶ坪型壺について」pp.189-197
・川崎みどり「元屋敷式と神明式の間」pp.198-206
・赤塚次郎「最後の台付甕」pp.207-214
・野沢則幸「名古屋市旧紫川遺跡出土の線刻文土器二点」pp.215-219
・神谷友和「愛知県安城市古井堤遺跡出土の条痕文土器」pp.220-228
85号『特集:早稲田20代人論集(3)』(1988年3月)
・高柳圭一「仙台湾周辺の縄文時代後期後葉から晩期初頭にかけての編年動向」pp.1-40・忍澤成視「縄文時代の生産用骨角器の在り方にみられる一般性」pp.41-60
・井上洋一「宮ノ台期における環濠の機能について(予察)」pp.61-68
・武井 勝「東国における富豪層の様相」pp.69-77
・柳澤清一「東北縄文中・後期編年の諸問題 その1 中期末葉の編年(中)」pp.78-118
・高橋龍三郎「セビリアンの起源と系統について(上)」p119-148
84号(1987年9月)
・関野拍夫「静岡県田方郡上白岩遺跡の検討―特に土坑の解釈を巡って―」pp.1-32・柳澤清一「東北縄文中・後期編年の諸問題 その1 中期末葉の編年(上)」pp.33-80
・佐々木彰「岩手県宮沢原C遺跡の復元―特に配石遺構を中心―」pp.81-109
・鈴木正博「続 大洞A₂式考」pp.110-133
・長谷川厚「歴史時代墳墓の成立と展開(2)―特に南武蔵・相模の火葬墓の成立をめぐって―」pp.134-162
・坂井 隆「インドネシア・バリ島の舟形石棺―その型式学的考察―」pp.163-177
83号『地域特集(3)―千葉県―』(1987年3月)
・西川博孝「田戸下層式土器―千葉県内の新資料を加えた検討―」p1-11・鈴木正博「大倉南・武田新・古原―千葉県先史遺蹟の再評価事始―」pp.12-36
・石坂俊郎「市川市国府台出土の弥生後期壺棺」pp.37-44
・比田井克仁「南関東出土の北陸系土器について」pp.45-82
・車崎正彦「房総豪族層の動向」pp.83-99
・白井久美子「祇園大塚山古墳の埴輪と須恵器」pp.100-109
・杉山晋作・大久保奈奈・荻 悦久「佐原市・禅昌寺山古墳の遺物」pp.110-139
・山路直充「市川市出土の軒先瓦について―中島辨智氏旧蔵品から2点の資料紹介―」pp.140-161
・栗田則久「旧香取郡出土の墨書土器」pp.162-191
82号『直良信夫先生追悼号』(1986年12月)
・滝口 宏「はしがき」pp.1-4・直良信夫「伊勢御正体厨子奉籠の五穀及び五薬について」pp.5-13
・直良信夫「マイルカの右側橈骨に突き刺さった石器」pp.14-16
・直良信夫「秩父市影森橋立洞窟発掘の動物遺体」pp.17-19
・春成秀爾「直良先生の命名された新種」pp.20-22
・杉山博久「直良先生と銅鐸の研究―忘れられたその研究分野―」pp.23-45
・江坂輝彌・芹沢長介・椚 国男・西村正衛・桜井清彦・前沢輝政・大川 情・久保哲三・金子浩昌・杉山荘平・石井則孝・吉川国男「追悼文」pp.46-67
・前澤輝政「関東地方における『外来系土器』の意味―三たび狗奴国考―」pp.68-92
・柳澤清一「加曾利E式の細別と呼称(中篇)」pp.93-142
・杉崎茂樹「行田市若王子古墳について」pp.143-151
・嶋村友子「河内における庄内式の甕形土器」pp.152-167
・ジム=アレン・関 俊彦「先史パプア・ニューギニアにおける食料探求への適応」pp.168-187
81号『特集:早稲田20代人論集(2)』(1986年6月)
・滝口 宏「序言」・松本 完「土器の機能(2)諸機能の素描」pp.1-24
・川本素行「打製石斧の分析」pp.25-50
・西川修一・石坂俊郎「千葉県柏市戸張城山遺跡の特殊な壺」pp.51-61
・佐々木幹雄「新出土の三輪山須恵器」pp.62-69
・稲田 晃「古墳の設計尺数―特異形前方後円墳での検討―」pp.70-83
・柳澤清一「竜ヶ崎市南三島遺跡出土の土器」pp.84-96
80号『西村正衛先生古稀記念 石器時代論集』(1985年12月)
・滝口 宏「序文―西村先生の古稀をお祝いして―」pp.1-2・今村啓爾「繩文早期の竪穴住居址にみられる方形の掘り込みについて」pp.1-19
・関野哲夫「茅山下層式土器について」pp.20-38
・山本暉久「繩文時代の廃屋葬」pp.39-71
・中山吉秀「房総における繩文前期後半の様相―特に諸磯式土器と浮島式土器の比較から―」pp.72-98
・芳賀英一「大木5式土器と東部関東との関係」pp.99-132
・谷井 彪「阿玉台式からみた東北南部大木式の変遷」pp.133-154
・柳澤清一「加曾利E式土器の細別と呼称(前編)」pp.155-177
・秋山道生「繩文時代中期後半における弧線文系譜―関東地方以西を中心として―」pp.178-213
・小川和博「堀之内2式土器の成立をめぐって」pp.214-227
・前沢輝政「中部地方における繩文時代晩期文化の地域性について」pp.228-240
・藤村東男「岩手県九年橋遺跡出土石剣類の損壊について」pp.241-257
・鈴木加津子「関東北の関西系晩期有分土器小考」pp.258-276
・青木幸一「繩文時代晩期終末土器の一視点―関東地方東部について―」pp.277-290
・平野吾郎「伊賀谷遺跡出土の土器について」pp.291-310
・堀越正行「関東における貝輪生産とその意義」pp.311-322
・馬目順一「閉窩式有鉤銛頭の地域的特性」pp.323-333
・中村五郎「繩文時代のシャーマニズム」pp.334-359
・渡辺 誠「唐津市菜畑遺跡等出土の組織痕土器について」pp.360-381
・鈴木正博「弥生式への長い途」pp.382-398
・田部井功「須和田式土器の一考察―特に系譜の検討をふまえて―」pp.399-417
・常松幹雄「西北九州における弥生時代後期土器様式の構成に関する一研究(後編)」pp.418-433
・新田栄治「広州・南越王墓出土『文帝行壐』金印について」pp.434-447
・スチュアート=ヘンリ「先史エスキモー文化の装飾について―極北四〇〇〇年間の『美術史』序説―」pp.448-475
・永峯光一「〔書評〕西村正衛著『石器時代における利根川下流域の研究―貝塚を中心として―』」pp.476-478
78・79合併号『地域特集(2)―東京―』(1985年3月)
・西村正衛「西ヶ原貝塚出土の石器」pp.1-2・鈴木正博「三宅島島下遺蹟13層の土器について」pp.3-13
・比田井克仁「外来土器の展開―古墳時代前期の東京を中心として―」pp.14-39
・谷川章雄「東京都大田区立蒲田小学校出土の古式土師器」pp.40-59
・小川貴司・寺田良喜「等々力渓谷2号横穴にみる交流について」pp.60-101
・安藤鴻基・井上裕一「浅草伝法院の『石棺』」pp.102-111
・石井則孝「戦後における都内の発掘について」pp.112-119
・長崎潤一「口絵解説 東早淵遺跡出土の局部磨製石斧」pp.59
77号(1984年6月)
・田中新史「出現期古墳の理解と展望―東国神門五号墳の調査と関連して―」pp.1-53・常松幹雄「西北九州における弥生時代後期土器様式の構成に関する一研究(前編)」pp.54-67
・瓦吹 堅「北茨城市八塚遺跡出土の土偶」pp.68-74
・大橋泰夫・荻 悦久・水沼良浩「常陸長辺寺山古墳の円筒埴輪」pp.75-83
75・76合併号『特集:早稲田20代人特集』(1983年12月)
・永沼律朗「鈴杏葉考」pp.1-28・白井久美子「小規模古墳の一類型について―ブリッジ付円墳の検討―」pp.29-69
・比田井克仁「古墳時代前期の丘陵地域小集落について」pp.70-87
・長谷川厚「歴史時代墳墓の成立と展開(1)―特に相模・南武蔵の火葬墓の様相を中心として―」pp.88-122
・西川修一「南関東における弥生~古墳時代土器研究史―その変遷と問題点―」pp.123-139
74号(1983年12月)
・比田井克仁「古墳時代前期高坏考―南関東地方を理解するために―」pp.1-34・米田耕之助「動物形土製品に関する一考察」pp.35-51
・原田昌幸「繩文時代の<はきもの>―町田市木曾町採集の土偶から―」pp.52-57
73号(1982年12月)
・前沢輝政「三遠式銅鐸の盛行地域について―狗奴国考―」pp.1-34・斉藤国夫「北武蔵における七世紀の動向―古墳からみた一側面―」pp.35-46
・鷹野光行「𩸽澗式と『ホッケマ式』」pp.47-52
・木下哲夫・工藤俊樹「福井市深坂町小繩遺跡試掘 調査略報」pp.53-65
・多宇邦雄・井上裕一・森田みつえ「早稲田大学所沢新校地周辺出土の遺物について」pp.66-70
・市毛勲「ベンガラ入れ小壺二題」pp.46
72号(1982年3月)
・鈴木正博「埼玉県高井東遺蹟の土偶について」pp.1-8・田部井功「縄文晩期・細密沈線文土器についての二,三の考察」pp.9-25
・小林茂・吉川國男「秩父市下ツ原遺跡の調査(一)」pp.26-37
・笹森紀己子「かまどの出現の背景」pp.38-48
・杉崎茂樹「埼玉県出土の須恵器を模倣した土師器について」pp.49-56
・石川裕子「埼玉県本郷貝塚の土偶」pp.57-60
71号(1981年12月)
・佐々木幹雄「三輪山及びその周辺出土の子持勾玉」pp.1-23・今村啓爾「柳沢清一氏の『称名寺式土器論』を批判する」pp.24-34
・米田耕之助「独鈷状石製品覚え書」pp.35-47
・白井久美子「市原市上総国分寺台出土の東海系『有段口縁』甕形土器について」pp.48-64
69・70合併号(1981年3月)
・西村正衛「序文」pp.1-4・浅田芳朗「鍬形石への二、三の関心」pp.5-27
・水野 祐「大津皇子謀反事件についての一考察―特に草壁皇子尊の年齢の誤謬より見たる事件真相に関する批判的考証―」pp.28-53
・岡田芳朗「歴史考古学と紀年法」pp.54-82
・西連寺健「いわゆる『北大式』省察野帳―北海道千歳市ウサクマイ遺跡群が提起する問題―」pp.83-118
・佐々木幹雄「三輪山出土の須恵器―土器観察表―」pp.119-137
68号(1980年12月)
・柳澤清一「称名寺式土器論(結編)」pp.1-40・遊佐和敏「所謂『帆立貝式古墳』の形態的分離について」pp.41-58
67号(1980年3月)
・リチャード=ピアソン(著)・関 俊彦(訳)「日本・朝鮮半島における古環境と集落」pp.1-16・鈴木正博「婚姻動態から観た大森貝塚」pp.17-30
・米田耕之助「繩文時代後期における一葬法」pp.31-38
66号(1979年12月)
・柳澤清一「称名寺式土器論(続)」pp.1-28・佐々木幹雄「三輪山出土の須恵器」pp.29-58
・市毛 勲「飛鳥の酒船石について―網干善教氏の批判を中心として―」pp.59-63
65号(1979年3月)
・柳澤清一「称名寺式土器論(中編)」pp.1-24・多宇邦雄・永沼律郎「みそ岩屋古墳の検討」pp.25-33
・須田 勉「房総の古瓦に関する覚書(2)―川原井廃寺跡―」pp.34-45
64号(1978年12月)
・米田耕之助 「所謂『軽石製浮子』について」pp.1-10・斉藤弘道・鈴木正博「日立市曲松遺跡の弥生式土器に就いて―型式学的研究を中心として―」pp.11-34
・安藤鴻基・杉崎茂樹・糸川道行・永沼律朗「千葉県香取郡小見川町三之分目大塚山古墳の長持形石棺遺材」pp.35-45
・須田 勉「房総の古瓦に関する覚書(1)」pp.46-59
63号(1977年12月)
・田中新史「市原市神門四号墳の出現とその系譜」pp.1-21・柳澤清一「称名寺式土器論(前編)」pp.22-60
・今橋浩一・長岐 勉 ・鈴木正博「常総台地に於ける縄文式後期前葉の土器群の一属性について」pp.61-65
62号『中村恵次君追悼合』(1977年3月)
・「中村恵次君追悼文」pp.1-16・「中村恵次君略年譜及業績目録」pp.17-21
・米田耕之助「千葉県六通貝塚出土の台付異形土器」pp.22-24
・安房国分寺調査団「安房国分寺第一次調査概報」pp.25-44
61号(1976年12月)
・須田 勉「上総国府の諸問題―特に所在地をめぐって―」pp.1-34・中山吉秀「離れ国分考」pp.35-59
59・60合併号(1976年9月)
・杉山晋作「房総の埴輪(一)―九十九里地域における人物埴輪の二相―」pp.1-15・市毛 勲「房総人物埴輪顔面の赤彩色法―人物埴輪顔面の赤彩色についてIV―」pp.16-25
・安藤鴻基「埴輪祭祀の終焉」pp.26-37
・車崎正彦「常陸舟塚山古墳の埴輪」pp.38-49
・橋本博文「東国への初期円筒埴輪波及の一例と位置づけ―群馬県朝子塚古墳表採資料の解釈のめぐって―」pp.50-69
・米田耕之助「上総山倉一号墳の人物埴輪」pp.70-80
・平野吾郎「遠江における片袖横穴式石室墳について」pp.81-91
・馬目順一「曾谷貝塚における抜歯人骨の調査」pp.92-100
・須田 勉「口絵 人面土器解説」pp.25
58号(1974年12月)
・金子浩昌「E・S・モースによって報告された大森貝塚出土の骨角製品、特に銛頭について」pp.1-16・鷹野光行「鶴塚遺跡出土の縄文式土器」pp.17-25
・市毛 勲・多宇邦雄「千葉県香取郡小見川町城山発見石棺群と城山六号墳の調査」pp.26-36
・穴沢咊光・馬目順一「『中華人民共和国出土文物ロンドン展』カタログの紹介」pp.37-39
57号(1974年3月)
・杉山晋作「変則的古墳の一解釈(その一)―前方後円墳の平面企画方法を通して―」pp.1-27・斉木 勝「千葉県向油田貝塚出土の石器」pp.28-34
・安藤鴻基「千葉県木更津市畑沢埴輪窯址の調査速報」pp.35-37
56号(1973年9月)
・市毛 勲「『変則的古墳』覚書」pp.1-29・杉山晋作「千葉県木更津市手古塚古墳の調査速報」pp.30-33
・早稲田大学考古学研究室「常陸における古墳の測量調査」pp.34-39
55号(1973年3月)
・前沢輝政「下毛野国曲ヶ島古墳群―栃木県下都賀郡岩舟町曲ヶ島所在―」pp.1-16・中村恵次・沼沢 豊「前方後方墳の一考察―千葉県市原市六孫王原古墳の調査―」pp.17-32
54号(1971年3月)
・前沢輝政「下野『塔法田堂址』は芳賀郡衙址である」pp.1-8・蒲田辰之・服部敬史「東京都八王子市中郷遺跡の調査」pp.9-24
・平野吾郎「愛知県北設楽町納庫麦田遺跡の調査」pp.25-45
53号(1970年3月)
・駒井和愛「隅田八幡画像鏡の年代とその銘文」pp.1-5・金井典美「神話と考古学―大和朝廷成立のアウトライン―」pp.6-25
・山本暉久「長野県和田峠発見の石器新資料」pp.26-32
・村田文夫「多摩丘陵東端発見の繩文前期末葉から中期初頭の土器について」pp.33-42
・橘 善光「青森県東通村白糠採集の土師器と擦文土器について―下北半島の擦文土器の成立に関する試論―」pp.43-50
52号(1969年3月)
・川崎純徳「茨城における弥生文化の成立について(試論)」pp.1-10・杉山博久・平野吾郎「神奈川県秦野市平沢同明遺跡の調査」pp.11-30
・馬目順一「いわき市小茶園遺跡出土の土器」pp.31-35
・金刺伸吾「印内町出土の太占について本郷町出土の墨書土器」pp.36-38
51号(1968年9月)
・金井典美「五世紀における畿内の祭祀遺跡と古墳分布 」pp.1-12・和田 哲「八王子市平町繩文前期遺跡」pp.13-30
・原 信之・馬日順一「宮城県大木囲貝塚発見の遺物について」pp.31-42
49・50合併号(1968年9月)
・定金右源二「『古代』五十号発行を祝して」・定金右源二「キプロスのトロスに就いて」pp.1-21
・直良信夫「東京都中野刑務所内竪穴発掘の炭化物」pp.22-24
・軽部慈恩「駿河国日吉廃寺址発掘調査の綜合結果」pp.25-45
・駒井和愛「漢代のうちわ」pp.46-48
・浅田芳朗「羽前赤湯の和銅開珎」pp.49-56
・山下孫継「秋田県雄勝町岩井堂岩陰遺跡の早期遺物」pp.57-74
・栗原朋信「上代の日本へ対する三韓の外交形式」pp.75-89
・奈良修介「秋田県の藤原鎌倉文化」pp.90-95
・滝口 宏・平野元三郎「大同元年在銘横穴」pp.96-106
・宇野信四郎「東京都北区飛鳥山遺跡の調査報告」pp.107-113
・藤沢宗平「押型文土器と住居址」pp.114-121
・桜井清彦「北海道尾白内貝塚出土の鉄器」pp.122-125
・大川 清「木更津矢那瓦窯址」pp.126-134
・岡田芳朗「和同開珎と平城遷都」pp.135-143
・金子浩昌「岡山県繩文諸貝塚出土の漁類遺骸―瀬戸内沿岸にみる繩文石器時代の魚労形態―」pp.144-151
・中村恵次・市毛 勲「富津古墳群八丁塚古墳調査報告」pp.152-164
・古代(自一号至五〇号)総目次 pp.166-173
・玉口時雄「『古代』五〇号の回顧」pp.174-174
・前沢輝政「下野国足利・岡瓦窯址」pp.22-36
・今井浤二・金沢和夫「佐渡島・藤塚貝塚調査報告」pp.1-21
48号(1967年3月)
・山内清男「縄紋土器の改定年代と海進の時期について」pp.1-16・中村恵次「千葉県山武郡土気町舟塚古噴の調査」pp.17-32
・桜井清彦・岡田威夫「長野県川上村二本木遺跡の調査」pp.33-39
・寺田兼方・原 信之「藤沢市高山出土の土器」pp.40-44
・佐藤信之「山形県江俣弥生式遺跡」pp.45-56
47号(1966年9月)
・前沢輝政「土製槨の火葬墓について―栃木県足利市久保田神明木出土―」pp.1-13・桜井清彦・平野吾郎「愛知県設楽町神田中向遺の調査」pp.14-30
・金井典美・石井則孝「長野県霧ヶ峯池のくるみ遺跡調査略報」pp.31-33
・大内幹雄・平山 猛「那珂湊市発見の後期弥生式住居址」pp.34-36
・椚 国男「八王子市舘野町和田出土の土師器」pp.36-38
・玉口時雄「土師器に描かれた線描絵画」pp.38-40
45・46合併号(1965年10月)
・西村正衛「千葉県取郡神崎町西ノ城遺跡―第二次調査概報―」pp.1-40・前沢輝政「足利公園古墳群中西南部円墳」pp.41-50
・黒崎康雄・橋本 晋「北海道浦河郡浦河町浜荻伏遺跡」pp.51-64
・渡辺一雄「福島県勿来市の古式土師器」pp.65-68
・伊東重政「絵画のある土師器」pp.69-72
44号(1965年2月)
・浜名徳永・市毛 勲「鮭の埴輪」pp.1-10・前沢輝政「下野国鑁阿寺の仏舎利について」pp.11-17
・関 俊彦「長野県下伊那郡出土の有孔磨製石鏃」pp.18-24
・宮坂光昭「縄文中期勝坂と加曽利E期の差―貯蔵形態の変遷から観て―」pp.25-31
・平山 猛・大内幹雄「茨城県勝田市薬師台貝塚」pp.32-35
・滝口 宏「小原一夫さんを悼む」pp.36-38
42・43合併号(1964年3月)
・中村恵次「千葉県養老川流域の古墳群についての一考察」pp.1-16・吉川国男・金井典美・石井則孝「東京都下久留米町 神明山ローム層中遺跡発掘調査概報―第一次―」pp.17-23
・中村竜雄「環状住居阯群と立石」pp.24-30
・金井塚良一「埼玉県比企郡吉見村和名出土の壺形土器」pp.31-36
・桐原 健「上総金鈴塚出土の巴形飾金具」pp.37-41
・金子浩昌「富士見台(犬吠)貝塚―縄文後期の漁撈と骨角器文化の一型―」pp.1-64
41号(1963年10月)
・菊地義次「印旛・手賀沼周辺地域の弥生文化―南関東系、北関東系弥生文化の混合地域としての特殊性―」pp.1-18・市毛 勲「東国における墳丘裾に内部施設を有する古墳について」pp.19-26
・渡辺 誠「福島県勿来市発見の土師系蔵骨器」pp.27-29
・坂井利明「下野国分寺出土の文様瓦について」pp.30-39
・亀山脩平「佐野市旗川流域の古代遺跡について」pp.40-44
・馬目順一「岩手県二戸郡発見の亀ケ岡式直後の土器」pp.45-50
39・40合併号(1962年10月)
・矢島恭介「熊野那智の遺物と金経門縁起」pp.1-8・軽部慈恩「百済の遺跡調査に残された将来の課題」pp.9-16
・直良信夫「富士火山噴出物下の廃滅農家の作物遺体」pp.17-26
・駒井和愛「オホーツク文化の年代について」pp.27-31
・浅田芳朗「短甲形埴輪覚書」pp.32-49
・藤沢宗平「繩文文化の滑石製品」pp.50-66
・前沢輝政「繩文式土偶の一考察」pp.67-72
・金子浩昌「石器時代貝塚出土のウナギとハゼの遺存骨について」pp.73-81
・川島守一「栃木県の古墳文化の様相に就て」pp.82-89
・石野 瑛「考古学と史学との相関」pp.90-95
38号(1962年7月)
・早大考古学研究会「三鷹市大沢御塔坂2・3号横穴」pp.1-22・前沢輝政「『首狩』についての人類学的考察―高松遺跡出土の人骨-頭蓋骨(推定)、下顎骨をめぐって―」pp.23-29
・市毛 勲「古墳時代の施朱について」pp.30-36
・馬目順一「爬虫類型動物把手の新資料」pp.37-40
37号(1961年12月)
・中村恵次・市毛 勲「千葉市中原古墳群調査報告」pp.1-21・松本豊胤「香川県善通寺市出土の弥生式土器」pp.22-32
・吉田順一「青石塔婆論」pp.33-44
36号(1961年3月)
・西村正衛「千葉県成田市荒海貝塚―東部関東地方縄文文化終末期の研究(予報)―」pp.1-18・栗原文蔵・横川好富「埼玉県寄居町発見の古代式土師器」pp.19-23
・中川成夫・岡本 勇・倉田芳郎・田村晃一「新潟県北蒲原郡豊浦村の考古学的調査予報―特に須恵器窯址を中心に―」pp.24-29
・滝口 宏「先島諸島の土器」pp.30-36
35号(1960年7月)
・西村正衛・金子浩昌「千葉県香取郡鴇崎貝塚」pp.1-26・早大高等学院歴史研究部「八王子市宇津貫町閑道第二号窯址」pp.27-37
・寺村光晴「新潟県引越遺跡出土の土器」pp.38-45
34号(1960年1月)
・西村正衛「利根川下流域における縄文中期文化の地域的考察(予報)」pp.1-32・坂詰秀一「相模南足柄出土の墨書土器」pp.33-35
・小田富士雄・黒野肇「筑前垣生遺跡発見遺物(一)」pp.36-42
33号(1959年9月)
・大川 清・佐藤俊雄・坂井利明・渡辺賢一「千葉市大金沢町左作瓦窯址」pp.1-12・桜井清彦・小松芳男・山田賢吾「新潟県高土村塚田第一号墳調査報告」pp.13-19
・金谷克巳「大和呉谷発見の蔵骨器」pp.20-22
・金子浩昌・中村恵次・市毛 勲「千葉県東葛飾郡沼南村片山古墳群の調査」pp.23-39
32号(1959年4月)
・桜井清彦・大川 清「東京都世田谷区岡本町横穴古墳調査報告」pp.1-12・井上義安「北茨城市足洗における甕棺調査の概報」pp.13-27
・椎名仙卓「佐渡金井村本屋敷出土の墨書土器」pp.28-30
・中川成夫「栗原遺跡出土の鉄製紡錘車」pp.31-32
31号(1959年1月)
・中山淳子・中村惠次「西戸山遺跡調査報告」pp.1-9・江坂輝弥「福島県下発見の蕨手刀」pp.10-12
・小田富士雄「墨書須恵器の新資料―豊前発見の地名神社名記載資料に関する一考察―」pp.12-14
・竹内秀雄・萩原弘道「東京都調布市入間町遺跡調査概報」pp.15-20
・坂詰秀一「千葉県富里村高野台出土の垂玉」pp.20-23
・黒野 肇「遠賀郡中間町唐戸遺跡」pp.23-26
・石橋謙治「千葉県神崎町古噴の概要」pp.1-10
29・30合併号(1958年10月)
・西村正衛・菊池義次・金子浩昌「岩手県大船渡市清水貝塚」pp.1-45・大川 清・田中義昭・西垣丹三「島根県益田市西平原窯址」pp.46-59
・櫻井清彦・和田 哲「練馬区貫井町三菱レイョン遺跡」pp.59-71
・長島 健「武氏祠画象の一画題」pp.72-74
・岡田芳朗「革命改元について」pp.75-82
・前沢輝政「両毛地方における地下式竪穴石室と古式古墳の関係について」pp.83-91
・平野元三郎「上総姉ケ崎火葬蔵骨器」pp.92-96
・滝口 宏・西村正衛・玉口時雄「落合遺跡第二次調査」pp.97-123
・「早稲田大学考古学研究室調査遺跡表(Ⅰ)」pp.1-12
28号(1958年5月)
・大川 清・坂井利明「東京都町田市小山町瓦尾根第一号瓦窯址」pp.1-13・前沢輝政「『地下式竪穴石室』調査報告―栃木県下都賀郡岩舟村中の島出土―」pp.14-22
・伊藤和夫「貝塚より見た千葉市附近の海進海退」pp.23-35
・井上 義・井上義安「女性埴輪の新資料」pp.36-37
27号(1958年2月)
・桜井清彦「北海道奥尻島青苗貝塚について(第一次調査概報)」pp.1-8 仲野誠一「千葉県香取郡神崎町久井崎遺跡」pp.8-9 井上義安「福島県磐城高校所蔵の弥生式土器」pp.10-12 高橋三男「東上総源六谷横穴群について」pp.13-3225・26合併号(1957年10月)
・藤田亮策「硬玉問題の再検討」pp.1-11 矢島恭介「播磨極楽寺の瓦経資料―酒井家旧蔵の拓影本について―」pp.1-20 軽部慈恩「千葉県山武郡大提権現塚前方後円墳の発掘調査」pp.21-31 駒井和愛「先秦中国の一発明―蒺藜」pp.32-35 浅田芳郎「埴輪起源説覚書」pp.36-43 日野一郎「中世墳墓の一形態―相模山北における鎌倉時代の墳墓―」pp.44-54 菊地義次「千鳥久保貝塚発見の骨角器を着装せる人骨に就て」pp.55-67 藤沢宗平「木曾における繩文文化より弥生文化への推移について」pp.68-77 前沢輝政「足利市八幡・山辺小学校裏古墳(二基)調査報告」pp.78-87 直良信夫「オホーツク海沿岸遺跡発掘の家犬下顎骨」pp.1-1624号(1957年5月)
・大川 清「上総光善寺廃寺」pp.1-12・井上義安「常陸笠谷遺跡出土の弥生式土器にい就て」pp.13-22
・坂詰秀一「北海道出土石刀の新資料」pp.22-24
・椿 逸雄「千葉縣香取郡神崎町古原採集の土器」pp.25-25
・小林 茂「武蔵熊谷市広瀬出土の蕨手刀」pp.26-28
・大川 淸「動物土偶 二例」pp.28-30
23号(1957年2月)
・早大考古學研究室「練馬區北大泉丸山遺跡」p1-22・佐々木修・菊池啓次郞「岩手県北上市口内町宝積古墓群の調査」pp.23-29
・川崎利夫「山形縣上荒谷繩文前期遺跡の土偶について」pp.30-31
・石橋謙治「千葉縣香取郡下總町前原遺跡」pp.31-32
21・22合併 号(1956年11月)
・西村正衛・金子浩昌「千葉縣香取郡大倉南貝塚」pp.1-47・若月 直「山梨縣岡部村出土の土師器」pp.48-51
・寺村光晴「新潟縣片貝町町浦出土の木製容器について」pp.52-54
・小杉秀雄・佐藤俊雄「芝山古墳郡小池第一號墳」pp.55-57
・東 登「氣仙沼地方の先史時代遺跡の分布略報」pp.58-64
19・20合併 号(1956年6月)
・滝口 宏・大川 清「栃木縣益子町栗生瀧ノ入窯址調査槪報」pp.1-20・金子浩昌「千葉縣香取郡東庄町の石棺調査」pp.21-24
・鈴木喜久二・中村繁治「千葉縣芝山古墳群殿塚第七號墳發掘略報」pp.25-29
・玉口時雄・小林 茂「秩父市下郷永田出土の土師器」pp.30-33
・小田富士雄「豊前京都郡久保村出土の天永元年銘經筒」pp.34-35
・井上義安「常陸足洗遺跡發見の彌生式甕棺」pp.36-39
・西村正衛「オーストラリア原文化とオセアニア及びインドネシアとの關係」pp.39-43
・「千葉縣芝山古墳群調査速報 」pp.49-64
・「古代(自一號至二十號)總目次 」pp.45-47
18 号(1956年2月)
・滝口 宏・西村正衛「秋田県雄勝郡欠上遺跡発掘報告」pp.1-7・小田富士雄「小形土壙墓の調査」pp.8-12
・久保哲三・工藤 稔「下野益子天王塚古墳調査予報」pp.13-17
・金谷克己「大和國新庄町發見の土製品」pp.17-18
・坂詰秀一「埼玉縣北足立郡安行出土の藏骨器」pp.18-19
・大川 清「記録に於ける視覚の利用-3-」pp.19-23
・洞 富雄「モルガン『古代社会』正誤」pp.24-27
17号(1955年9月)
・滝口 宏「岩手縣北上市黑岩白山廢寺」pp.1-12・櫻井淸彦「青森縣相内村赤坂遺跡について」pp.16-21
・江坂輝彌「石鍬の一新例」pp.22-23
・下津谷達男「千葉縣小金町發見の土師器」pp.23-26
・大川 淸「記録に於ける視覺の利用(二)」pp.27-32
16号(1955年7月)
・前澤輝政「佐野市八幡山古墳調査概報」pp.1-10・金子浩昌・川村喜一「葛生会沢石炭岩裂罅中の堆積物に就いて」pp.11-17
・金谷克己「紀伊国妙寺町発見の石棒」pp.18-20
・江坂輝彌「田戸住吉町系文化文献目録」pp.21-23
・大川 清「記録に於ける視覚の利用」pp.24-34
14・15合併号(1955年5月)
・滝口 宏「市川市須和田奈良時代遺跡」pp.1-40・滝口 宏「調査及び遺跡の性格」pp.1-9
・川村喜一「第一號住居址」pp.10-17
・玉口時雄「第二號住居址」pp.17-23
・玉口時雄「V字形溝狀遺構に就いて」pp.23-33
・金子浩昌「須和田遺跡出土の炭化大麥―古代麥作農業とその遺物」pp.33-40
・菊池義次「南武地方橫穴群に就いて―特に久ヶ原台地附近を中心として見たる―」pp.41-65
・天野義雄・渡邊隆一「大田區田園調布ドリコノ坂橫穴古墳調査槪報」pp.66-69
・渡邊包夫・實藤 遠「上總大多喜町高谷の古墳」pp.70-74
13号(1954年6月)
・水野 祐「隅田八幡神社所蔵鏡銘文の一解釈」pp.1-17・玉口時雄・大川 淸「上総上瀑村打岡台の古墳」pp.18-23
・中川成夫「大田区上池上町所在横穴について」pp.24-27
・江坂輝弥「廻転押捺文系文化文献目録」pp.28-36
12号(1953年11月)
・日野一郎「笠塔婆 」pp.1-15・江坂輝弥「青森縣下北半島稲崎遺跡調査報告」pp.16-24
・久保哲三・玉口時雄「下総竜角寺古墳調査概報」pp.24-27
・西村正衛「千葉縣君津郡三ツ作貝塚發見の早期繩文式土器」pp.27-30
11号(1953年9月)
・内藤政恒「古瓦より見た奈良朝地方文化相の一傾向―関東・東北の特異な地方文化相の分析―」pp.1-16・滝口 宏「エトロフ島の土器」pp.17-20
・小岩末治「盛岡市大館堤遺跡調査報告」pp.21-24
・大川 清「千葉縣印旛郡阿蘇村栗谷古墳」pp.25-29
・菊池啓次郎・桜井清彦「岩手縣鬼柳村古墓群調査報告」pp.29-32
10号(1953年7月)
・桜井清彦・西村正衛「青森縣森田村附近の遺蹟調査概報―第二次調査―」pp.1-18・前沢輝政・滝口 宏「足利市本城両崖山東麓古墳調査報告」pp.19-28
・平井尚志「ラロトンガ島の石斧」pp.29-30
・小林 茂「秩父出土の尖底土器」pp.30-32
9号(1953年1月)
・滝口 宏「上総大多喜の古墳」pp.1-7・菊地義次「久ヶ原遺跡に於ける弥生式堅穴調査・予報」pp.8-17
・大川 清「千葉県香取郡昭栄村地蔵原第1号古墳」pp.18-30
・大川 清「図書紹介『加茂遺蹟―千葉縣加茂獨木舟出土遺跡の研究』―三田史學会」pp.31-32
7・8合併号(1952年11月)
・安藤更生「洛陽大福先寺考」pp.1-6・駒井和愛「高麗朝の觀音像」pp.7-10
・直良信夫「栃木縣葛生會澤の一遺跡」pp.11-16
・洞 富雄「トジ・エヌシ・ヤンヌシ考」pp.17-21
・滝口 宏「上代に於ける方位の決定について」pp.22-27
・西村正衛「千葉縣香取郡八都村向油田貝塚發掘槪報」pp.28-44
・桜井淸彥「福島縣相馬郡大野村竪穴發掘調査槪報」pp.45-47
・玉口時雄「上總飯野村西谷古墳調査報告」pp.48-51
・大川 清「住居址に於ける燒土について」pp.52-59
・前澤輝政「日本考古學の根本問題」pp.61-63
・西村朝日太郞「温古知新」pp.64-68
6号(1952年8月)
・石野 瑛「横濱兜塚古墳撥掘調査報告」pp.1-12・神尾明正「金鈴塚の砂と石とについて 」pp.13-15
・江坂輝彌「関東地方の繩文式文化研究参考文献目録附形式名遺蹟所在地」pp.16-21
・「昭和二六年度本研究室夏季實習報告」pp.22-26
5号(1952年4月)
・栗原朋信「伝阿房宮故基出土瓦當の製作時代について」pp.1-13・大場磐雄「東北地方の祭祀遺跡(下)」pp.14-24
・西村正衛・桜井淸彦・玉口時雄「青森縣森田村附近の遺跡調査概報」pp.25-41
4号(1952年2月)
・大場磐雄「東北地方の祭祀遺跡(上)」pp.1-11・洞 富雄「母系制より父系制への推移―大化前代の族制―」pp.12-22
・大川 清「伊豆大島大久保遺跡予報」pp.23-26
3号(1951年9月)
・大場磐雄「三輪山麓發見古代祭器の一考察―延喜式所載祭器との關聯―」pp.1-9・直良信夫「宮城縣上川名貝塚発掘の家犬の遺骸」pp.10-25
・西村正衛「千葉縣香取郡神里村白井雷貝塚發掘概報」pp.26-31
・玉口時雄・金子浩昌・大川 清「印旛沼出土の刳舟」pp.32-38
1・2号合併号(1954年4月)
・直良信夫「南スエーデンに於ける農耕文化」pp.1-2・西村正衛 ・中澤 保「神奈川縣横濱市港北區下田下組西貝塚」pp.3-20
・大川 淸「日本古代栓状鏃の用途について」pp.21-25
・神尾明正「土器の顯微鏡薄片」pp.26
・桜井清彦「津輕考古記」pp.27-30
・前澤輝政「繩文文化から彌生文化への移行期を中心とする兩文化に於ける經濟生活の豫見」pp.31-35
・直良信夫「岡山縣邑久郡長濱村サブカセ五一三九番地出土の土獸(土師器出土の遺跡)」pp.36-37
・大川 清「北方文化圏出土の婦人像」pp.38-41
・玉口時雄「西上總金鈴塚古墳發掘豫報」pp.42-44
・桜井清彦「最近に於けるソ聯考古學の一面」pp.45-47
・滝口 宏「下總龍角寺圓墳」pp.48-51
・淺香勝輔「圖書紹介『日本社會經濟史』(第一巻)」pp.52-53